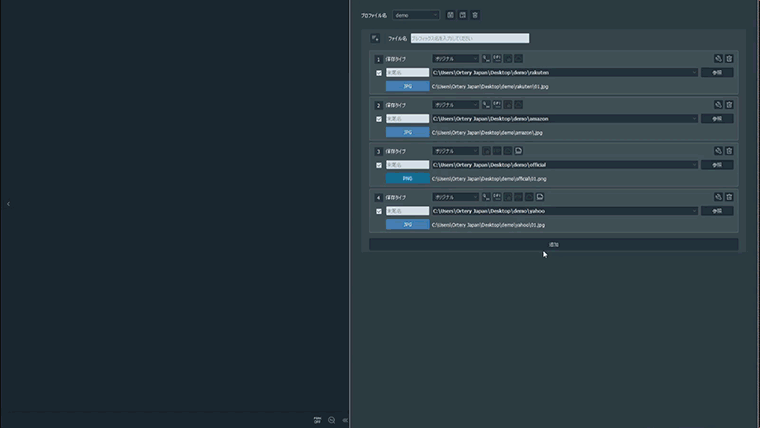ECサイトのささげ業務とは!勘違いしやすいささげの重要度
ECサイトのささげとは?
ECサイトの運営においてのささげの意味とは、「撮影(さつえい)」「採寸(さいすん)」「原稿(げんこう)」の頭文字を取った3つの業務のことを「ささげ」と言います。
ささげ業務はお客様がECサイトで商品を購入するか否か決める重要ポイントである、商品ページの重要箇所を担っていることが念頭に置かなければならないです。
お店でいう店員、販売スタッフの役割をしていくれる大事な業務なのです。
撮影は、ディスプレイ
採寸は、試着
原稿は、肌触り、スタッフからの提案、言葉
このように置き換えると非常に重要であることはお判りいただけたと思います。
ささげ業務のそれぞれの役割と押さえておきたい注意点
ささげ業務の「さ」=撮影
最初は「撮影」。ここでいう撮影には、商品撮影と画像編集・画像加工が含まれいることを忘れてはいけないです。「ささげ業務」の中で一番時間がかかるものとなります。
また唯一、テクノロジーで全面カバーできていない分野です。商品撮影には、カメラの知識、ライティングの知識など専門知識が含まれ、画像編集には色味加工や背景切り抜き(白抜き加工)が入っており、こちらも専門知識が必要です。
「ライティング」「背景」「カメラ」この三つに関わるコツを学べば撮影時の失敗は防げます。より良く見せるにはそこから派生した専門的なスキルが必要ですが、ECサイトに掲載して、スマホできれいに見えるくらいの撮影は難なくこなせるでしょう。
商品撮影は非常に奥深く、知識や考え方一つでコンテンツの持つ力が大きく変わることを覚えておきましょう。白い商品は白くなりすぎず、白く見えるように、黒い商品は黒くつぶれないように、できるだけ黒くし、色味の深いものは色がしっかり出るようにライティングを正確に整えていく必要があります。
また先にお伝えした通り、店頭でいうディスプレイにあたるものなので、ここが重要視していない企業は、店頭に並べられた商品をぐちゃぐちゃに並べているのと同じであることを認識しましょう。
ささげ業務の「さ」=採寸
ECサイトやオンライン上でサイズを把握するために欠かせない「採寸」。
ZOZOTOWNが、ブレークする前は洋服、アパレルを通販で購入するのはすごくハードルが高いと言われていました。
そのハードルの一つが「サイズ問題」です。サイズが数センチ違うだけで、全く違うフォルムになるため、mm単位で表示するところがほとんどです。要するにECサイトでの洋服選びはサイズがシビアに考えられている証拠でもある捉えられます。
サイズ表記ミスは、すぐに返品&クレーム対象になるため、正確性を保ちつつ、素早くこなしていきたい箇所です。
少し昔のようにやりがいのない仕事でも忍耐力を持って続けていく人が少なくなる環境・社会になっているので、将来的にECの業務における、ささげ業務で一番縮小率が大きくなる可能性が高い分野です。
やりがいの多い業務と兼任をさせて、うまくモチベーションをコントロールさせることが重要です。
ささげ業務の「げ」=原稿
ECサイトには欠かせない「原稿」。ECサイト上で商品の魅力をテキストで表現をしていくのが、原稿の役割です。
原稿は店頭で洋服や靴、アクセサリーに触れた時の感触、肌触り、ぬくもり、生地感とそれをどう合わせるといいのかという店員さんからのアイディアや提案がこちらに置き換わっています。
画像や動画で概要を確認できれば原稿を読まずに購入している人が多いのも確かです。画像にテキストを載せている企業が多いのはそのためです。
SASAGE.AIはアパレル企業に特化したツールで、物撮りやトルソー、平置き、ハンガー撮影後にモデルが着用している合成画像を作れたり、画像解析で採寸をしたり、原稿を書いてくれたりと、面倒な業務をテクノロジーの力で解決してくれるツールです。
原稿は購買意欲の高い人が見ると言われている部分ですが、疎かにできる部分ではないので、ユーザーの訪問意図や購買意欲をそそる文言にすること、画像では伝えきれない質感や手触り感を表現するのはテキストの役目となり、画像と合わせて相乗効果を生む重要な箇所です。
ささげ業務を内製化するメリット
ささげを内製するメリットは主に以下の項目が挙げられます。
① 時間短縮:外注に充ててた時間を撮影時間にして時間ロス0
② 納期:即日~翌日にデータ完成→機会損失が減る
③ 掲載カット数:数倍に増加
④ SEO/マーケティング施策:連動性が高まる
⑤社内スタッフ:クリエイティブの関心が高まる
⑥クオリティ:アップ
⑦SNS:撮影クオリティUPで、フォロワーの増加
⑧営業・販促:商品の使用イメージが豊富に
データの納品スピード
ささげ業務を最大のメリットはここにあります。確かに社内で行うにはリソース配分も考えなくてはならないため、面倒なのですが、ささげのチームが中にいるとコミュニケーションが円滑に進むため、データを納品できるスピードが格段に違います。
また、部署やチームの設立から長くなれば、自社独自のルールの運用ノウハウが溜まり、教育コストも少なくなるため更に効率化とクオリティ向上が見込めます。
マーケティングとの連動の優位性
先述した社内でのコミュニケーションの円滑性は、マーケティングにも大きな影響を与えられます。
どのようなニーズを満たすとお客様が喜ばれるかを理解し、コンテンツに落とし込むことで、顧客やユーザーの購買意欲の向上にすぐに直結させることができます。
例えば、Tシャツの厚みが知りたいけど、○○オンスと言われても…となります。
「素肌に着ても透けにくい厚さで~」と画像を添えれば、ユーザーニーズは簡単に満たせます。
画像引用:KIBACOWORKS公式サイト
在庫や納品データをコントロールできる
ささげ業務あるあるで、急ぎで掲載や撮影を進めたい商品があった場合、それを外注に頼むとささげの費用も高くなることやコミュニケーションコストを普段より多く割かなければいけないため、担当や会社にとっても多くの犠牲を払います。
自社で行える場合、撮影スケジュールを調整し、割り込ませるだけになるので、さほど犠牲を払わずに済むため、業務のコントロールがしやすくなります。管理する側としては、ストレスも負荷もかかりにくいため、頻繁にスケジュール調整が入りそうであれば、内製化を強くおすすめします。
ささげ業務を内製化するデメリット

離職率が高くなる傾向がある
ささげ業務は一部にツールを導入できるとは言え、まだまだアナログな世界で、人材集約型で時間もコストもかかる業務です。単純な作業にも関わらず、テクノロジーでは代替えできない部分も多く、離職率が高くなる傾向にあります。
教育コストがかかる
ささげ業務は現場の仕事であるが故に、地元の方がアルバイトやパートで活躍されている現場です。どの現場も単純作業であるため、納品期限と日々の撮影量を一定に保つために教育するコストがかかります。
人材もなかなか確保できない時代なので、経験者を雇うことはほぼできないため、教育コスト(時間や費用)は、以前よりもかかりやすい傾向です。
業務の進捗管理が大変
ささげ業務管理するために基幹システムを導入されている企業やエクセル等で業務管理されている企業は割とガチガチに業務スケジュールが決められており、順調、遅延などが把握されていて、その後の業務に影響が出ないようにコンテンツ制作の一部を分担して行っていきます。
この管理業務だけで日々何時間と費やしている企業があるくらいなので、アナログでの管理を考えている方は、フルフィルメントでささげ業務を行っている企業などの基幹システムなども含めて考えておくといいでしょう。
ささげ業務の外注をする際に押さえておくべきポイント
ささげ業務の外注コスト
外注にはコストがつきものです。社内の人ではなく、外部の人を動かすので、その外部の人件費+利益が上乗せされるため、自社で行うより、高くなる計算になります。コストは安い方がいいですが、安ければいいわけではなく、目的に合わせたコスト設定が必要です。
とにかく安くするということであれば、リードタイムも長くなる、品質も悪くなる、編集はしてもらえないなど様々な条件が付いてくるでしょう。その内容とコストが見合っていれば払った方が、安い場合もありますので、コストではなくコストによる効果がどれだけあるかを見極める必要があります。
商品撮影のリードタイム
コスト同様に、早ければ早いほど、いいのですが、早いと弊害も出てくるでしょう。撮影が雑、編集が雑、撮影数が少ない、コストが高いなど。スピードとコスト、コストとリードタイムはとトレードオフの関係なので、アナログの作業が一般的なため、総取りは難しいのが現状です。
商品を送ってからどれくらいでデータが納品されるか、商品が返ってくるかは機会損失に繋がる重要事項なので、様々な会社の話を聞いてみるといいでしょう。
商品画像の品質
画像の品質については、昨今よく話題に挙がっています。ECサイト用の画像であれば、正直なところ、アマチュアでも撮影ができるようになっています。情報社会になって、ブラックボックスに入っていた部分が明るみに出てきて、アマチュアのクオリティが上がっていることが背景にあります。
何を気を付けるべきかというと、2点あります。
①自社の基準としているクオリティが出せるかどうか
②自社の基準としているクオリティがどれくらいのリードタイムで出せるかどうか
ここの設定を間違えると外注企業が悪者になりかねないので注意が必要です。
業務のボリューム
ここが一番大事な要素で、どこの業務ボリュームを増やそうとしているかの目的がズレると、ただの銭失いの取り組みになります。
例えば、マーケティングに時間を使いたいから撮影業務を委託するということであれば、効果が出ると思います。しかし、撮影クオリティを上げるために外注をするということであれば、失敗する可能性が高いです。
また、自社でノウハウを持っていないから撮影は外部に…というパターンも目的があやふやで、余計なコストがかかっている企業が多くいます。撮影のボリュームをなくして、どこのボリュームを増やすかその部分を明確にした上で外注企業を選んでみてください。
ささげ業務の本質

ここでは、あまり語られないささげ業務の本質について、お伝えします。テクノロジーの発展が著しい現代に、なぜささげ業務のほとんどが今までと変わらずアナログ業務で構成されているのか考えたことがない方はぜひご覧ください。
ECサイトのユーザー視点はささげ業務から
一番大きな部分を占めているのは、ユーザー視点でコンテンツを作ることが目的だからです。時々、今までの風習や慣習に沿って、メーカーや小売の本位で商品撮影、画像編集をされている企業を見かけます。
時代の流れによってユーザーが見る場所、考え方が変わるのに、画像の見せ方やコンテンツの内容が変わっていかないことは、リスクを大きくするだけです。
ユーザーが何を求めていて、どんなことに興味を持っているのか、買った後はどんなことを考えているのかを軸に考えればコンテンツが変わっていくことは必然です。
一つ事例をご覧ください。日本を代表するアパレル会社のユニクロです。ユニクロのECサイトの掲載コンテンツについて、簡単に見ていきます。
5年ほど前は商品ページの画像は5枚ほどで構成されていましたが、その後360度アニメーションが導入され、現在は商品ページの画像枚数は7枚から10枚になっており、注力している商品にはGIFアニメーションが組み込まれていて、時代の流れを常に見て、打つコンテンツを変えていることがわかります。
売れるECサイトのコンテンツの具現化はささげ業務でする
ユーザー視点で捉えることは、ユーザーが見たいコンテンツを出すことなので、売れる商品画像、編集を作り、見えやすい場所に配置し、伝わりやすいように構成することが売れる画像であり、「売れるコンテンツ」です。上記の例のように、ユーザーが求めているコンテンツは日々変化していきます。
消費者になるとこうしたらもっとわかりやすいのに、こんなコンテンツがあるといいのになど考えられるのに、売る側に立つと途端に作り手のエゴが先行してしまいます。買い手と売り手のギャップがある商品ページはオンラインショッピングの戦国時代には致命傷になりかねません。
では、そのギャップをなくすにはどうすればいいのか。答えは非常に簡単です。売るための行動ではなく、”売れるため”の施策と考えをマーケティング部署や経営層だけでなく、現場にも浸透させる必要があります。なぜこのカットが必要なのか。なぜ制作に時間のかかるコンテンツが必要なのか、納得を得た上で撮影始めるとそうでないのでは、業務への取り組む姿勢やスピードが格段に変化します。
現場の方からも意見を吸い上げ、カメラマンのエゴとマーケターのエゴだけをユーザーに押し付けるのではなく、ユーザー視点で、現場から変えていくことで、今後もブランドや店舗を愛してくれるファンがより一層増える方法なのではないでしょうか。
まとめ
ささげ業務はただこなせばいいわけではない
ここまでお伝えしてきた通り、EC業界でよく使われる「ささげ業務」は単にこなしていけばいいだけの業務ではないことはご理解いただけたと思います。
ささげ業務の撮影、採寸、原稿は末端業務であるため、考えがおろそかになったり、管理下に置いてない管理職の方も多いですが、何か大きなことをリスクを取ってやる前に「ささげとは?」を理解し、改善に取り組めば、ライバル企業にはないインフラが整い、短期的にも、長期的にも大きな利益をもたらすことは間違いないです。
ささげ業務関連部署の離職率の低下、業務効率の向上、生産性の向上、従業員満足度が改善されることで、数か月で数百万、1年で1000万以上の効果が出ることも珍しくありません。
規模の大小ではなく、効果の大小、価値提供の多さが関係していますので、これから取り組まれる企業様は撮影インフラの設計を間違えないようにする。
商品撮影を社内でされていて、ささげの悩みが絶えない企業様はインフラの根底にある課題を早めに引っ張り出して改善をしていくことをお勧めします。
国内600社以上EC事業者が使う商品撮影システム
ライティングは自由自在で設定保存もできる
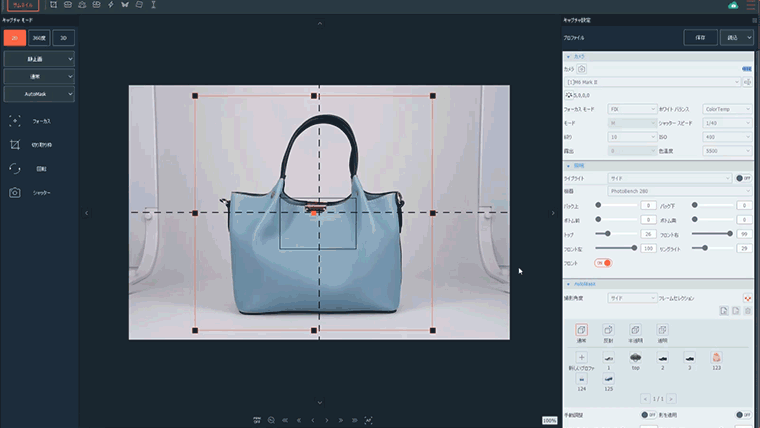
技術はいらない!商品撮影と背景切り抜きを同時にやる
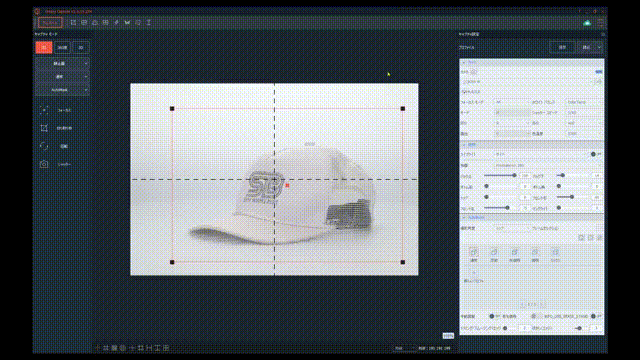
今まで教育が大変とされていた、カメラの技術が会社にノウハウとして溜められるとなると業務が円滑に進めらます。
自動撮影システムでは、撮影と同時に背景処理も5秒で行うため、編集の時間も大幅に削れます。
撮影した画像は、リネーム、リサイズ、形式変換、フォルダ振り分けを複数パターン一気に保存できるため、撮影、編集、加工のトータル工数と時間が1/3も夢じゃないです。
リサイズ、リネーム、出力先指定も自動で